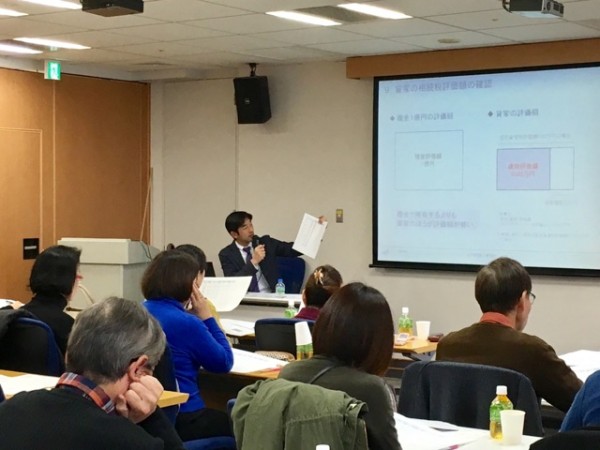HOME >BLOG
路線価が付されていない宅地の評価方法
相続税や贈与税を計算する場合における宅地の評価の方法は,都市部(市街地的形態を形成する地域にある宅地)では路線価方式,それ以外では倍率方式によることになっています。
路線価とは国税庁が日本全国の路線(道路)に1㎡当たりの価額を付したものをいい,路線価方式とは,その路線価に地積を乗じて宅地を評価する方法をいいます(実際には個々の宅地の事情や利用形態により各種調整を加えます)。
例えば,評価しようとする80㎡の宅地が接している道路の路線価が500千円のとき,500千円×80㎡=4,000万円というように評価します。
しかし,国税庁も全ての道路に路線価を付しているわけではありませんので,「路線価の設定されていない道路のみに接している宅地」というのも結構な割合で存在します。
そのような宅地は,次の2つの方法のうちどちらかの方法で評価します。
①道路に接続する路線の路線価を基に画地調整を行って評価する。
②申出により特定路線価を設定してもらい評価する。
①の方法は,評価したい宅地と,その周りの宅地を合わせて評価し,その全体評価額から周りの宅地評価額を控除して間接的に評価する方法です。
②の方法は,納税義務者からの申出により,国税庁が個別に路線価を設定し,これを基に評価するという方法です。この個別に設定された路線価を特定路線価といいます。
どちらの方法で評価するかは納税義務者が判断することになりますが,国税庁としては①の方法で評価することを原則とし,それが実情に即していない場合には②の方法を認めるとしています。
実務上は何をもって「実情に即していない」と判断するかは非常に難しい問題ですので,どちらの方法を選択するかは個別に判断することになります。
特定路線価の申出をする場合は,「特定路線価設定申出書」に所定の事項を記載して,所轄税務署へ提出します。通常は1ヶ月程度で「特定路線価回答書」として,特例路線価が設定されます。
特定路線価の申出をして特定路線価が設定されますと,原則としてその特定路線価を必ず使用しなければなりません。
想定していたよりも特定路線価が高く設定されたからといって,①の画地調整を行って評価する方法によることはできません。
これに関する明文の規定はありませんが,国税不服審判所の裁決事例(H24.11.13裁決)によると,一旦,特定路線価が設定されますと,画地調整を行って評価する方法によることはできないと読み取れます。
「特定路線価を設定して評価する趣旨は,評価対象地が,路線価の設定されていない道路のみに接している場合であっても,評価対象地の価額をその道路と状況が類似する付近の路線価の設定された路線に接する宅地とのバランスを失することのないように評価しようとするものであって,(中略)このような趣旨からすると,特定路線価は,路線価の設定されていない道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基にその道路の状況,評価しようとする宅地の所在する地区の別等を考慮して評定されるものであるから,その評定において不合理と認められる特段の事情がない限り,当該特定路線価に基づく評価方法は,(中略)画地調整を行って評価する方法より合理的であると認められる。」
路線価が付されていない宅地の評価は非常に難しい問題ですので,特定路線価の申出をするか否かを含め,慎重に対応したいところです。
セルフメディケーション税制と医療費控除について
平成29年1月1日より,医療費控除の特例制度である「セルフメディケーション税制」(以下,SM税制)が施行されました。今回はこの制度をご紹介します。
※セルフメディケーションとは,世界保健機構において,「自己の健康に責任を持ち,軽度な身体の不調は自己で手当てすること」と定義されています。
<制度の趣旨>
我が国のこれ以上の医療費の膨張を防ぐため,一部の市販薬を購入したときに所得控除を受けられるようにすることで,広く国民に健康診断を適正に受診させ,軽度な身体の不調は医療機関にかからずとも,市販薬等を使い自己で治すように促すことが目的です。
<制度の概要>
SM税制とは,健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う居住者が,平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に,自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合に,その金額が1万2千円を超えるときは,その超える部分の金額(上限8万8千円)を総所得金額等から控除する,というものです。
尚,従来からの医療費控除との選択制で,併用は認められません。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組とは,要するに予防接種や健康診断のことです。例としては以下のようなものがあります。
・健康保険組合や市区町村が実施する健康診断
・インフルエンザ等の予防接種
・勤務先が実施する定期健康診断(事業主検診)
・メタボ検診
尚,任意で全額自己負担で受診した健康診断は,SM制度の対象外です。
特定一般用医薬品とは,医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から,ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。
具体的な対象商品は約1,500品目あり,風邪薬から胃腸薬,貼付薬まで幅広く,厚生労働省のHPに一覧が掲載されています。
<従来の医療費控除との関係>
従来の医療費控除は,病気や怪我の治療又は療養に必要な医薬品の購入費用は控除対象となりますが,病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入費用は控除対象となりません。
これに対し,SM税制は,病気等の治療に限定せず,税制対象スイッチOTC医薬品の購入費用であれば控除対象となります。
SM税制は「医療費控除の特例」という位置付けのため,従来からの医療費控除との併用はできません。
よって,従来の医療費控除を適用した場合と,新しいSM税制を適用した場合とで,どちらを選択した方が有利となるかを計算する必要があります。
<適用を受けるための手続き>
従来の医療費控除と同様に,対象商品を購入したレシート等を確定申告書に添付又は提示する必要があります。レシート等には,次の5つの事項の記載が必要です。①商品名,②金額,③当該商品がSM税制対象商品である旨の記載,④販売店名,⑤購入日
また,SM税制は予防接種や健康診断を受診していることが要件の一つですので,次の証明書等を申告書に添付又は提示する必要があります。
①インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証
②市区町村のがん検診の領収書又は結果通知書
③職場で受診した定期健康診断の結果通知
④特定健康診査の領収書又は結果通知書
⑤人間ドッグやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知書
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
現在,相続手続では,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
例えば,被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合,その相続人は,まずA市に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を提出して相続登記を行い,A市の登記が完了したらその戸籍謄本等の返却を受け,次にB市に提出するといった具合です。
同時進行も可能ですが,その場合はA市とB市に同じ書類を同時に提出しなければならず,戸籍謄本等の取得費用が2倍になってしまいます。
このような事情から,近時,相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し,これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっていると指摘されています。
そこで,相続登記を促進するために,法定相続情報証明制度が新設されました。この制度を利用することで,各種相続手続きで戸籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。
制度の概要は以下の通りです。
(1)申出(法定相続人又は代理人)
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集
②法定相続情報一覧図を作成
③申出書を記載し①②を添付して提出
(2)確認・交付(登記所)
①登記官による確認,法定相続情報一覧図の保管
②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付
(3)利用
各種相続手続の際に利用(戸籍謄本等の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に)
尚,この制度は,戸籍謄本等の束に代替し得る制度を追加するものですので,これまでどおり戸籍謄本等の束で相続手続を行うことを妨げるものではありません。
また,被相続人名義の不動産がない場合(例えば,遺産が銀行預金のみの場合)であっても利用することが可能です。
申出をすることができるのは,被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む)です。
代理人となることができるのは,法定代理人のほか,①民法上の親族,②資格者代理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士)です。
申出をすることができる登記所は,次の地を管轄する登記所のいずれかです。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は,一覧図の写しの再交付が可能です。
但し,再交付を申出することができるのは,当初,一覧図の保管等申出した申出人に限られ,他の相続人が再交付を希望する場合には,当初の申出人からの委任が必要です。
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸籍謄本等を収集することができない場合には,この制度は利用できません。
相続手続のメインは不動産と預貯金です。不動産の相続登記については,この制度により格段に効率が良くなるものと思われます。預貯金については金融機関次第ですが,是非この制度の趣旨を理解し,相続手続の効率化に協力して頂きたいものです。