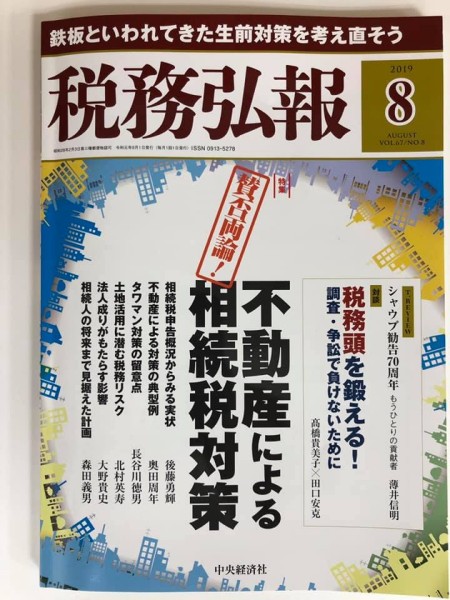HOME >BLOG
無理な消費税還付
不動産賃貸業に携わっている人であれば「消費税還付」というキーワードを耳にしたことがあると思いますが,無理な消費税還付は否認されることもあるので注意が必要です。
消費税は,その事業年度における「売上げに係る消費税」から「仕入れに係る消費税」を控除し,その残額がプラスなら納税し,マイナスなら還付を受ける仕組みになっています。ただし,控除することができる「仕入れに係る消費税」には様々な制限があります。
不動産を購入する場合,土地は消費税非課税ですが建物は消費税課税なので,居住用賃貸不動産を購入しますと建物に係る多額の消費税を支払うことになります。
一方で,その事業年度に収受する家賃は建物対価よりも一般的には少額ですので,売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を単純に控除すると必ずマイナスになります。ただし,居住用賃貸不動産の場合,収受する家賃そのものが消費税非課税ですので,支払った仕入れに係る消費税を直接控除することはできず,仕入れに係る消費税に課税売上割合を乗ずることで,控除する消費税を制限しています。
式で表すと次のようになります。
A 売上げに係る消費税
B 仕入れに係る消費税×課税売上割合
A-Bがプラスなら納税,マイナスなら還付
課税売上割合とは,その事業年度における総売上に占める課税売上の割合のことですが,居住用賃貸不動産から収受する家賃は非課税売上ですので,その家賃だけしか収入が無い場合,課税売上割合は0となります。つまり,控除することができる消費税は0となり,消費税の還付を受けることはできません。
そこで,消費税還付を受けるべく様々なスキームがこれまで考案されてきて,その多くが税制改正で封じ込められてしまったものの,未だ活用されている方法が金地金スキームです。
金地金スキームは,金地金の売買を繰り返し,課税売上を作為的に作り上げることによって課税売上割合を大きくし,控除することができる仕入れに係る消費税を多くする方法です。
実際に実行する場合にはこれをベースに様々な調整が必要になりますが,やり過ぎて否認されるケースもあるので注意が必要です。
最近公表された否認事例の概要は以下の通りです。(平成31年(行コ)第90号,平成31年(行コ)第96号)
Aは居住用賃貸不動産の購入に係る売買契約を締結した課税期間(引渡しはまだ受けていない)に建物に係る消費税を計上し,同課税期間に金地金の売買を行って作為的に課税売上割合を100%にして消費税の還付申告を行いました。税務署は建物に係る消費税を計上できるのは実際に引渡しを受けた翌課税期間であるとし,Aの申告を否認しました。Aが自己の申告の正当性を主張して国を訴えたものの,東京地裁及び東京高裁ともにAの訴えを退けました。
Aが正当性を主張した根拠は次の通達です。
消費税基本通達9-1-13「固定資産の譲渡の時期は,別に定めるものを除き,その引渡しがあった日とする。ただし,その固定資産が土地,建物その他これらに類する資産である場合において,事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときは,これを認める。」
この文章だけを読むとAは間違っていないとも思われますが,この通達には,不動産については一般的にその引渡しの事実関係が外形上明らかでないことが多いので契約基準も認めることにしているという前提があります。決して自己の都合の良いように選択性を認めているわけではなく,原則は引渡基準であることに変わりはありません。常識で考えればわかることですし,奇をてらい過ぎるとこのように否認されるので注意が必要です。
参考:税務通信No.3575
※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。
非居住者への不動産譲渡は要源泉徴収
所得税は,自らがその年の所得金額とこれに対する税額を計算し自主的に申告・納税する「申告納税制度」が建前です。
これと併せて特定の所得については,その所得の支払者がその支払の際に所得税を源泉徴収して納付する「源泉徴収制度」が採用されています。
この源泉徴収制度で最も一般的なのは会社が支給する給与等です。
給与等の支払者はその支払の際に,所得税を源泉徴収して国に納付しなければなりません。
これを源泉徴収義務といいます。
この源泉徴収義務は「義務」ですので,源泉徴収を怠ると罰則があります。
正当な理由なく納期限までに完納されなかった場合には納付すべき金額の10%に相当する不納付加算税が課されます。
さて,この源泉徴収制度ですが,会社が支給する給与や報酬及び配当等については比較的周知されていますので所得税を源泉徴収することを失念することは余りないのですが,不動産取引においても源泉徴収義務を有する場合があるので注意が必要です。
不動産取引において源泉徴収義務を有する場合とは,非居住者又は外国法人から一定の不動産を購入する場合です。
すなわち,非居住者又は外国法人から国内にある不動産を購入する場合には,その対価の支払をする者はその譲渡対価に対して10.21%の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し,国に納付しなければなりません。
ただし,購入する者が個人であって,自己の居住用に取得する場合で,かつ,対価の額が1億円以下である場合には源泉徴収の必要はありません。
ところで,所得税法における居住者と非居住者の区分ですが,居住者とは「国内に住所を有し,又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」をいい,非居住者とは,「居住者以外の個人」をいいます。
また,住所は,個人の生活の本拠をいい,生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定します。
したがって,居住者か非居住者であるかについて国籍は関係ありませんし,住所がどこであるかについて住民票の有無は関係ありません。
住民票が日本に無い外国人であっても,日本に1年以上居住していれば居住者に該当することはありますし,反対に,住民票が日本にある日本人であっても,客観的事実に基づく住所が外国にある場合には非居住者に該当することもあります。
一般的に不動産取引をする場合,仲介業者を介することが多く,プロでない限り売主と買主が直接やり取りすることはまれですが,仲介業者が必ずしも源泉徴収制度を承知しているとは限りません。
もし仮に,仲介業者が源泉徴収制度を知らず,売主が非居住者であるにもかかわらず売買代金の全額を売主に渡してしまったら,源泉徴収義務違反となり,譲渡対価の10.21%を買主が国に納税しなければなりません。
加えて,その源泉税の10%に相当する不納付加算税も課税されます。
結果として二重に支払ったこととなる源泉税については,当然,売主に返金請求することはできます。
できますが,相手が返金してくれるか否かはわかりません。
売った不動産が居住用であれば売主は引っ越しするでしょうし,それが外国であれば連絡を取ることも容易ではありません。
運良く連絡が取れたとしても,返金を拒否されたら,現実的には取立ては難しいです。
源泉徴収を失念した場合であっても,源泉税の本来の「負担者」である売主から国が直接徴収すれば良いという意見を耳にしますが,法律上の「納税義務者」はあくまでも買主ですので,国が売主に課税処分をすることはありません。
東京五輪以降,不動産価額が縮小すると予想する声も大きく,非居住者や外国法人が多くの不動産を売却するかも知れません。
そのタイミングで不動産を購入する場合には,くれぐれも源泉徴収義務にご注意下さい。
※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。
遺留分制度の見直し
遺留分制度とは,被相続人の有していた相続財産について,一定の相続人に一定の割合での承継を保障する制度です。
被相続人は,原則として,生前贈与や遺言により自己の財産を自由に処分することができますが,特定の相続人だけにすべての財産を相続させるという遺言を残していた場合,本来であれば自宅や預貯金を相続できたはずの他の相続人が何も相続できず,その後の生活に支障を来すということも考えられます。
そこで,被相続人が特定の相続人等に偏った遺言を残していた場合であっても,他の相続人が遺留分権利者である場合には,その遺留分権利者は遺留分の範囲内において相続財産を取得しうる権利(遺留分権)が与えられます。
この場合において,この遺留分権は行使される必要がありますので,遺留分が侵害された遺言が残されていた場合であっても,遺留分権利者が遺留分権を行使しなければ,その遺言の効力は有効となります。
遺留分権利者となる者は,配偶者,子,直系尊属です。兄弟姉妹は遺留分権利者とはなりません。
遺留分の割合は相続人が被相続人とどのような身分関係にあったかによって決まります。具体的には次のとおりです。
・相続人が直系尊属のみ・・・被相続人の財産の1/3
・上記以外・・・・・・・・・被相続人の財産の1/2
平成30年民法改正前は,遺留分権が行使されると,原則として遺留分の割合に応じて相続財産すべてが当然に共有(準共有)となっていました。
そのため,共有関係を解消するためには共有物の分割手続が必要となったり,相続財産が事業用財産であるのに事業に関与していない相続人にも事業用財産の共有持分が生じたりして,円滑な事業承継の妨げになるという問題が生じていました。
そこで遺留分制度の見直しが図られ,今後(令和元年7月1日施行)は,遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求(遺留分侵害額請求権)をすることができるようになりました。
この改正により,これまでは遺留分権の行使により当然に相続財産の共有関係が生じていましたが,これを回避することができるようになりました。
また,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をされた場合に,請求された側に金融資産が無いことも予想されますので,裁判所の許可を得て,相当期間の支払猶予を認めることとなりました。
この遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が,相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき,相続開始の時から10年を経過したときは時効により消滅します。
上記のとおり,改正後は遺留分権の行使は遺留分侵害額請求権という金銭債権となったわけですが,請求された側に現金又は預貯金が無い場合,有価証券や不動産等の資産をその支払に充当することが考えられます。
この場合において,その支払に充当した資産は譲渡したものとして所得税及び住民税が課税されますので注意が必要です。
この点,民法改正前において遺留分権の行使により土地が共有となり,当該土地を共有持分に応じて分割する場合にはその分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱われるのと異なります。
※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。
貸し駐車場に関する相続税の取扱いについて
未利用の土地を相続した場合や,誰も居住していない居住用不動産を相続した場合には,そのままではもったいないですから土地の有効活用を検討するものの,賃貸用建物を建築して賃貸事業を行うほどの事業リスクは負いたくない,というケースは意外と多いです。
このような場合には貸し駐車場としての土地活用が有効です。そこで,今回は貸し駐車場に関する相続税の取扱いを概観します。
貸し駐車場にはさまざまな形態があり,どの形態を選択するかはその土地の場所,地積,形状,投下できる費用等を総合勘案して決定することになりますが,選択した形態によって相続税における財産評価額及び小規模宅地等の特例の適用の有無に違いがあります。
駐車場の形態としては,おおよそ次の4つが考えられます。
- 月極駐車場(アスファルト舗装等)
- 月極駐車場(青空駐車場)
- コインパーキングを自営する。
- コインパーキング業者に賃貸する。
財産評価について
それぞれの形態における土地の財産評価ですが,上記1から3は,いずれもその土地の所有者が自ら貸し駐車場として利用していることになりますので,更地と同様にその土地の自用地としての価額により評価します。
貸地ではなく自用地として評価するのは,土地の所有者が,その土地をそのままの状態で(又は土地に設備を施して)貸し駐車場を経営することは,その土地で一定の期間,自動車を保管することを引き受けることであって,このような自動車を保管することを目的とする契約は,土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係であり,この場合の駐車場の利用権は,その契約期間に関係なく,その土地自体に及ぶものではないと考えられるためです。
上記4は,コインパーキング業者に土地を貸し,当該業者が貸し駐車場を経営しているケースですが,この場合の権利関係は土地の賃貸借契約に該当しますので,その土地の自用地としての価額から,賃借権の価額を控除した金額によって評価します。
この場合における控除する賃借権の価額は,おおむね次のように評価します。
自用地としての価額 × 次の区分に応じ次の割合
賃借権の残存期間05年以下・・・・・・2.5%
賃借権の残存期間05年超10年以下・・・5%
賃借権の残存期間10年超15年以下・・・7.5%
賃借権の残存期間15年超・・・・・・・10%
小規模宅地等の特例について
小規模宅地等の特例は,被相続人が所有していた自宅敷地や事業用土地の評価額を減額してくれる特例です。
貸し駐車場に対して考え得る小規模宅地等の特例は,特定事業用宅地等としての80%減額か,貸付事業用宅地等としての50%減額かのいずれかですが,大前提として,駐車場業は特定事業用宅地等に該当する「事業」から除かれており,その規模,設備の状況及び営業形態等を問わないこととなっています。
よって,貸し駐車場が特定事業用宅地等に該当することはありません。
次に,小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は,建物又は構築物の敷地となっている必要がありますから,アスファルト舗装や砂利敷き等の設備を有する必要があります。
そうしますと,上記1から4のうち,2の青空駐車場のみが小規模宅地等の特例の適用が無いということになり,他は貸付事業用宅地等としての50%減額が適用されます(面積制限有り)。
このように,貸し駐車場の形態によっては財産評価や小規模宅地等の特例の適用の有無に違いがあります。
貸し駐車場を始めるのはそれほど難しくないと思われますが,費用をかけずにロープと車止めだけで済ましますと,小規模宅地等の特例が適用されず,相続税におけるその影響額は小さくありませんので注意が必要です。
※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。